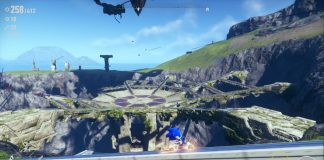打ち出し口から銀色のボールを射出し、やがてそれはキノコ型のバンパーに跳ね返り、フィールドを縦横無尽に目まぐるしく駆けめぐる……。プレイヤーはそのボールを落とさぬよう左右のフリッパーを巧みに操り、ときには台を揺らす。
たとえばファミリーコンピューターで『スーパーマリオブラザーズ』を遊んでいた場合、穴に落ちそうになったマリオに対してコントローラーや画面を動かしたところで何ひとつ変化は起きない。しかしピンボールは「TILT」という罰則が下りない限りは台を左右へ小刻みに、もしくは手前から奥へ突くように揺らし、ボールを落下させないこともテクニックのひとつとして認められている。
定められたルールとフィーチャーをひとつずつ理解することはスコアを飛躍的に伸ばすための原則だが、フィールドにボールが3球現れる「マルチボール」に突入したときは脳内のドーパミンが一気に止めどなく溢れ、さながら「ピンボール・ハイ」にすら達するほどの麻薬的快感すら覚えそうになる。突き詰められるだけの奥深さがありながら、シンプルで取っつきやすい遊びやすさを兼ね備えており、ファミリーコンピューターをはじめとする家庭用ゲーム機にも多くのソフトを揃え、WindowsXPまでは付属のゲームアプリとしてプリインストールされるなど、幅広い層に親しまれている。
しかし実機のピンボール台は、いまや一部のゲームセンターやバーでしか目にすることができない。90年代初頭まではゲームセンターでビデオゲームとともに肩を並べて稼動していたのがまるで嘘のように思えるが、あくまでも減少しただけであって、世界からピンボールが滅んだわけではない。愛好者によって愛されながら、かつてのプレイヤーには懐かしさを、若年層には目新しさを提供し続けている。
そんなピンボールがいま日本でどのように扱われ、そして先細りしていく未来に対してどんなアプローチをかけるのだろうか。当記事では販売や店舗向けレンタルを行なう業者や、現在でもピンボールを設置・稼動している店舗にインタビューを刊行。普段はビデオゲームをプレイするユーザーへのアクションとして、ピンボールの魅力や面白さに少しでも興味を持ってもらえれば本望である。
今回はピンボールの実機をゲームセンターやバーにリースしている有限会社マインドウェアの取り組みを特集。1987年にMNM Softwareとして創業し、古くは『アルガーナ』(X1)や『スターウォーズ アタック・オン・ザ・デス・スター』(X68000)の開発や『スラップファイト』(メガドライブ)などの移植を行い、近年ではSteamにて『宇宙最大の地底最大の作戦』や『スペースマウス』をリリースするなど、マイコンや家庭用ゲーム機のソフトウェアを開発・販売している。一見するとピンボールとは離れているように思えるが、ホームページアドレスが「http://pinball.co.jp/」となっており、ゲームの開発と並行してピンボールのレンタルや販売も行なっていることが窺える。
レンタルのきっかけは他店舗でのメンテナンス
――マインドウェアさんでピンボールをリースで扱われるようになったのはいつからでしょうか?
市川氏:
1996年からですね。僕が大きな病を患ってしまい、会社を一度たたんでしまったんです。それから回復し、これからどうしていこうかというときはすでにプレイステーションやセガサターンが出たころで、小さな会社が作るゲームなんて相手にされない状況だったんですよ。でも少人数なので「俺らだけが(業界内で)生きられればいいや」と思いつつも、世界中のみんながこっちを向いてくれるような「ガツンと心に響くもの」を作らないと楽しくないだろうと考えたんですよ。そこからピンボールのゲームを作ろうと決意し、出来のいいPC用ピンボールゲームを作るためには実機に詳しくないといけないということで死ぬほど遊びました。
――ちなみにピンボールは十代のころからアーケードゲーム同様に遊ばれていたのでしょうか?
市川氏:
昔からちょこちょこと触ってはいたのですが、ちゃんと遊び始めたのは1995年からですね。僕自身がかなり凝り性なので「なんとなくやる」っていうのはしないんですよ。で、このころからピンボールの設置台数が減り始めたことに加えて、メンテナンスされてないピンボールも増えてきたんです。それこそ『スペースインベーダー』以前からアミューズメント業界にいたメンテナンス屋さんみたいな人が定年を迎えている状況で。池袋のゲーセンを全部合わせて100台近くあったのが、その一年でたったの数台だけに減ってしまったんです。
――きっちりとメンテナンスされていないと「ただ置いてあるだけ」になってしまい、自然とプレイヤー離れを招き、結果的には店側も撤去せざるを得なくなっていたわけですね。
市川氏:
ええ。ちなみにそのとき僕は『Jack・bot』という台を猛烈にやり込んでいたんですけど、府中の「エスクワイヤ」っていうゲームセンターで、このシリーズの始まりとなる『Pin・bot』を見つけたんです。でもフリッパーが動かないどころかそもそも電源が入らないほどボロボロの状態だったので「納得いく状態で遊びたいので僕らがパーツ代も出すしメンテナンスさせてください」って何回か交渉してようやくOKをもらったんです。その店が閉じるときに「君たちさえよければ持っていってくれ」って言われて、ありがたく頂いたんですよ。
――パーツの仕組みや配線、80年代中期からはCPUも使われ始めるなど、内部構造も非常に複雑になったと思われるのですが、メンテナンスの方法についても独自に調べられたのでしょうか?
市川氏:
それもありますし、大きいのはJohn Popadiuk(WMS Gamingに属していたピンボールデザイナー)と親しくなってからで、特に1997年からは兄弟のようなお付き合いをさせてもらっているんです。リペアを学んだというよりは、その場にいるとピンボールのことはなんでもできるようになってしまうんですよ。Williamsの人たちはみんなプレイヤーとしてもスーパープレイヤーだから自分も感化されていきましたね。
――そうしてPC用ピンボールソフトを作るための研究でとことん遊び尽くしていたはずが、結果的にはそれを譲り受けることになったと。
市川氏:
そうなんですよ(笑)。いろんなお店に足を運んで「メンテナンスさせてほしい」っていう交渉を繰り返していくうちにどんどん台数が集まり、それからうちでピンボールのレンタルをするようになったんです。そうしたら、あるときうちのメカニックスタッフが「PCや家庭用ハードのピンボールゲームを作ってもロマンがないけど、これだけ台数があるんですし、実機のピンボールを作れたらすごいじゃないですか」と言いだして、その瞬間からPC向けのピンボールゲームっていうのがどうでもよくなったんですよ。それで2003年の夏に新小岩にあったゲームセンター「オモロン」で実機のロケテストまでやったんです。まさしくそれが、いまSteamで配信している『Pinball Parlor』なんです。
ライセンスに頼らざるを得ないことへの危惧
――『Pinball Parlor』のお話をお聞きする前に、まずピンボール業界ではWilliams(Bally)が1999年を機にピンボール事業から撤退し、そして長らくStern一社の時代が続きました。ピンボールが滅ばずに済んだ功績は大きいと思いますが、その反面として市場を独占する一強となったことでプレイヤーからは不安視されているところもありましたが、市川さんはどのようなお気持ちだったのでしょうか?
市川氏:
Data East(現:Stern)という会社はWilliams(Bally)がヒット作を出すとパクるんですよ。『The Addams Family』がウケれば似たような台をすぐに出すし、映画やドラマのライセンスは先行取得するくせに、肝心の台は『The Addams Family』を劣化させたようなルールばかり。最近のSternの台は面白くなってきているなとは思いますが、やっぱり90年代のWilliamsのクローンにしか見えないし、完全新規デザインではなくライセンスものに頼らざるを得ない。そうするとピンボールだけの力で売れているわけではなくなっちゃうんです。でもいまはほとんど個人売りになってしまっていて、ライセンスに思い入れのあるお金持ちに買ってもらうビジネスになってしまっているので、オリジナルで出せないとなるとピンボール自身で打開する力が一生つかなくなってしまうのではないかと危惧しています。そういう意味ではWilliamsはすごい正直にゲームを作る会社でしたね。
――『The Addams Family』からミニゲームと呼ばれるミッションクリア型のルールが広まりましたが、先ほどもお話にありましたとおり、店舗ではなく個人ユーザーによる購入が多くなっていることからルールが複雑化したと推測しています。
市川氏:
僕らってピンボールを遊びたいのであって、お勉強したいわけじゃないんですよね。でも、いまの台はルールシートがA4で40枚を超えるんじゃないかというぐらいの規模になってしまっているので、複雑化の一途をたどるのもちょっとどうかなと思ってるところもありますね。ピンボールに限らずビデオゲームも同じなんですが、シンプルでちゃんと説得力があるものを考える研究っていうのが行われてないんですよ。「多い」と「深い」っていうのは違うということをそろそろわかってほしい。あとは人の根源である「押し引き」の葛藤がゲームにはないとダメかなと思っていて、理的な押し引きの葛藤がないということは状況変化がないんですよ。人によって「こっちにしようかな、あっちにしようかな」っていうのがないということは、必ず「こっちがいい」ということが決まってる。でもそれってゲームじゃないんですよね。
――100円を入れて3球遊べるうち、最初の1stボールでひたすらマルチボールを狙うか、堅実にミニゲームをこなしていくかというのも、プレイヤーによって戦略が異なりますよね。
市川氏:
もっとシンプルな状況で言えば右フリッパーで打つのか、左フリッパーで打つのかというのもありますね。そうじゃないとプレイヤーの感性って出ないんですよ。押し引きの葛藤が不足しているといえば、フリッパーの配置がどの台もほとんど同じで、構造が何ひとつ変わってないところですね。Williams社内で出来上がった『Monster Bash』のプロットタイプを最初に遊んだ日本人は僕なんですが、1stボールでビッグゲーム(※)まで到達してしまったんです。それってつまりフリッパー周辺が変わってないままだから、ディフェンスが毎回同じなんですよ。みんなが遊ぶゲームっていうのは初級者も上級者もわりと同じぐらいのスタートラインから遊べるからこそ楽しまれるわけなんだけど、でも過去の積み上げがそのまま新しいゲームに活かされてしまう。だからプレイする人がどんどん限られるんですよね。
次ページ: 『Pinball Parlor』で解決したという不満点とはいったい?